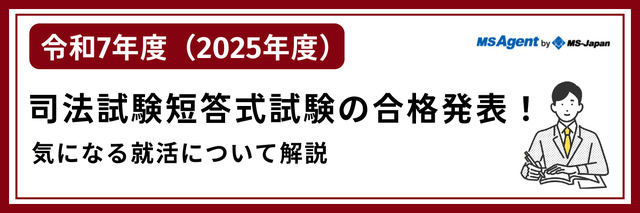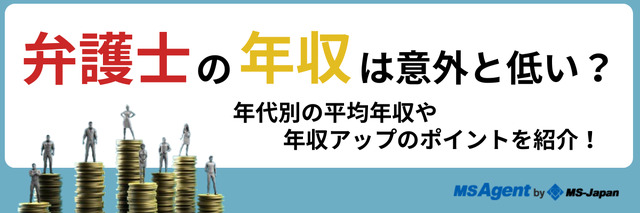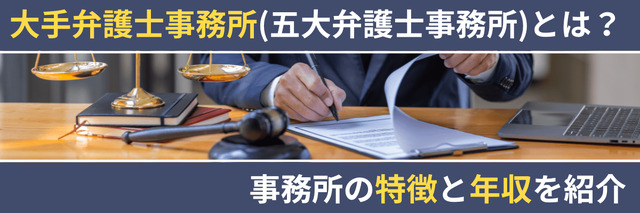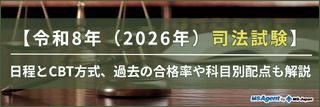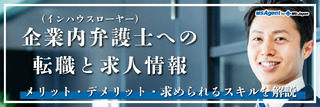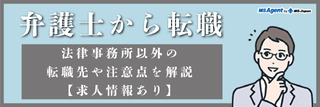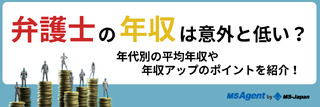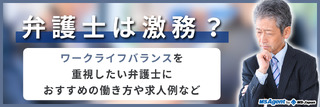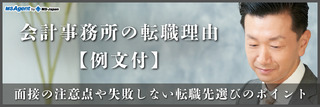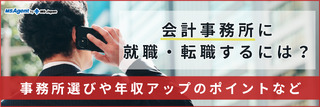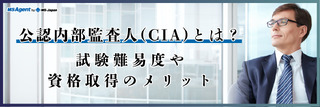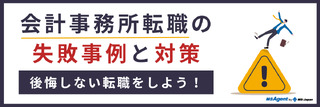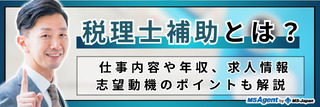弁護士が独立開業したら年収はいくら?独立にかかる費用やメリット、デメリットについて

弁護士としての実務経験を積み、年収アップやキャリアアップを目的とした独立を考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、いざ独立を検討するとなると「どれくらい費用がかかるのか」「デメリットはあるのか」「本当に稼げる?」など気になることはさまざま考えられます。
そこでこの記事では、弁護士が独立する際の費用、メリットとデメリット、年収などについて解説します。現在、独立を希望している方だけでなく、将来的に独立も選択肢の1つとして考えている方でも参考になる内容です。
弁護士の平均年収は?
まずは弁護士白書を参考に弁護士全体の平均年収を見てみましょう。
ここで紹介するデータの母集団となる弁護士は、開業弁護士、勤務弁護士、組織内弁護士、官公庁に勤務する弁護士など、さまざまな就業形態の弁護士が含まれています。
| 項目 | 収入 | 所得 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,082.6万円 | 1,022.3万円 |
| 中央値 | 1,500万円 | 800万円 |
全体の平均、中央値としては上記の結果となりました。
より詳細に、年次別でも見てみましょう。
| 経験年数 | 平均収入 (中央値) |
平均所得 (中央値) |
|---|---|---|
| 5年未満 | 575万円 (550万円) |
351万円 (300万円) |
| 5年以上 10年未満 |
1,252万円 (1,027万円) |
685万円 (650万円) |
| 10年以上 15年未満 |
1,975万円 (1,800万円) |
989万円 (860万円) |
| 15年以上 20年未満 |
2,554万円 (2,100万円) |
1,252万円 (1,100万円) |
| 20年以上 25年未満 |
3,763万円 (2,950万円) |
1,692万円 (1,215万円) |
| 25年以上 30年未満 |
3,220万円 (2,680万円) |
1,298万円 (1,000万円) |
| 30年以上 35年未満 |
2,687万円 (2,200万円) |
908万円 (695万円) |
| 35年以上 |
1,937万円 (1,300万円) |
734万円 (459万円) |
年次によって大きく差があることがわかります。
独立を検討する場合には、独立後の事務所売上から必要経費を差し引いた金額が、自らの年次の平均収入を超えてくるか否かが1つの判断材料になりそうです。
弁護士の独立に必要な初期費用は?
弁護士が開業に必要な資金は、一般的には300万円程度からといわれています。
開業に必要な資金を大きく分けると「場所に関する資金」「備品に関する資金」に分けられます。
場所に関する資金
場所に関する資金は、開業資金の中でも大きな割合を占めるものです。自宅開業であれば当然場所に関する資金は安く済みますが、クライアントとの打ち合わせには個人情報等の機密情報が洩れない場所も必要なため、オフィスを借りることが一般的です。
シェアオフィスを借りれば賃料等の費用を抑えることができるため、開業費用を抑えたい場合には検討しても良いでしょう。弁護士向けのシェアオフィスであればクライアントとの打ち合わせの際にも使用でき、登記も可能なため弁護士業務に支障なく使用できます。
また、テナントとして入る場合は、保証金もかかり、賃料の半年~1年分ほどになるため、保証金だけでも100~200万円ほどは必要になります。加えて礼金や仲介手数料、内装工事の費用もかかるため、テナントに入居する場合は300万円以上は準備しておく必要があるでしょう。
備品に関する資金
備品に関する資金としては、パソコン、電話機、複合機、オフィス用品などが挙げられます。とくに複合機は買取の場合100万円以上かかるケースもあるため、備品レンタルサービスなどを活用することで費用を安く抑えられます。
デスクやワーキングチェアなどのオフィス用品は個々人のこだわり次第ですが、クライアントに安心感・信頼感を与えるためにオフィスインテリアにもそれなりの資金を投じるケースが多いです。すべて自前でそろえる場合、備品に関する資金は数十万円~100万円程度を見込んでおく必要があるでしょう。
その他の資金
開業当初に必要な資金は上記2点になりますが、開業後にも資金はかかります。まずは、当面の運転資金です。すでに十分な売上が立つほどの個人クライアントがいるなどの一部のケースを除き、事務所運営が軌道に乗るまでの運転資金は用意しておくべきです。運転資金は1カ月の経費×3~6カ月分ほどが一般的といわれています。
また、昨今では事務所のホームページを制作している弁護士がほとんどのため、業者にもよりますが50万円前後のホームページ開設費用も必要でしょう。
弁護士が独立した後、継続的に必要な費用は?
独立した場合、継続的に必要な費用として、次のようなものがあります。
事務所の賃料
必ずかかる経費の1つが事務所の賃料です。共益費や消費税などを合わせて、30万円から50万円程度かかります。
賃料を抑えたい場合にはレンタルオフィスなどを契約する方法もありますが、相談者のプライバシーが守られ、安心して相談できる環境をつくるという観点で、共有オフィスは不向きな点があるのも事実です。
コピー機のリース代
裁判所に提出する書類の印刷など、弁護士業務ではコピー機が必要なシーンが多く、事務所にコピー機は欠かせません。
リースで導入することが多く、月1万円から1万5千円程度の費用がかかります。
通信費
独立にあたり、インターネット環境や電話回線の整備も必要です。これらの環境維持には通信費がかかり、その金額は月2万円から3万円程度です。
光熱費
冷暖房やパソコン、冷蔵庫、コピー機など、事務所には多くの電化製品を設置しなければなりません。これらを使用する電気代(光熱費)も必要です。一般的に月1万円から2万円ほどかかります。
広告費
独立時の知名度や専門領域などにもよりますが、多くの場合、集客のために何らかの広告が必要です。その際には広告費を払わなければなりません。
広告費は媒体や手法、露出量などによって大きく異なります。自社のSNSなどを活用すれば1カ月あたり0円ですが、有名なメディアに広告を掲載すれば30万円以上の費用がかかることもあります。
弁護士会費
弁護士会費も独立後の継続的な費用の1つです。加入する地域などにもよりますが、月額5万円程度かかります。
判例検索
判例検索サービスを契約する場合も費用がかかります。独立直後はサービス会社の営業が多く、キャンペーンが利用できることも少なくありません。月額おおよそ5千円から1万円程度で利用できるサービスが多いです。
雑費
上記以外にも書籍代や、来客用のお茶代、備品代などの雑費がかかります。
また、もし事務員や他の弁護士を雇うとなれば、当然ながら人件費も発生します。
これまでに挙げた費用をまとめると、事務所を構える立地(家賃)にもよりますが、毎月50万円ほどは必要経費がかかると考えておくとよいでしょう。独立直後は資金に余裕がないケースも多いため、経費を節約する意識は非常に重要です。費用をかけすぎている項目はないか、確認しましょう。
弁護士が独立した場合の年収は?
独立した場合、弁護士としての年収は事務所の売上に比例します。売上が多ければ、弁護士の年収相場よりも高くなりますが、逆に売上がふるわなければ、相場ほどの年収にはなりません。
ここで、上記で紹介した毎月の必要経費を50万円(東京での家賃+その他の経費:従業員なし)と仮定して年収のシミュレーションを行います。
月の売上平均が100万円の場合、1年間の売上は1,200万円です。毎月50万円、1年間で600万円の経費がかかるため、年収は600万円ということになります。
当然ですが、そこから利益の一部を会社にプールする場合、その分年収も下がります。
もし、売上から必要経費(年間600万円)を差し引いた額すべてを年収として得る場合、年収1,000万円を達成するには1カ月につき133万円の売上が必要です。
同様に、年収2,000万円を得るためには、毎月216万円の売上が必要となります。
さらに、売上が増えて事業規模が拡大していけば、人員を増やす必要もあるでしょう。その際は、人件費も加えた必要経費を考慮して、年収をシミュレーションしなければなりません。
年収を考えるにあたって重要なことは「目標年収と必要経費から、月あたりの売上目標を立てる」ということです。
月の目標が明確になれば「刑事事件」「離婚協議」「債務整理」など、分野ごとの相談件数目標も立てやすくなります。
また、独立すると「自身の収入」だけではなく、会社が利益として確保しておくべきお金なども考慮する必要があるためその点も留意する必要があります。
年収だけじゃない!独立をするメリットは?
弁護士として独立するメリットとしては、下記の5つが挙げられます。
- ・働き方を選べる
- ・自分次第でビジネスの幅を広げることができる
- ・経営に関する具体的なアドバイスができるようになる
- ・定年退職がない
- ・仕事を受ける相手や事件を選べる
それぞれ解説します。
働き方を選べる
独立することで、勤務時間や休日などを自分で決定できるようになります。
雇われている場合は、勤務時間や休日は固定されていることがほとんどですが、独立すれば縛りがなくなります。在宅勤務やリモートワークだけでなく、旅先での仕事も可能になります。
自分を律するという大変さはありますが、仕事とプライベートのメリハリをつけやすいのは大きなメリットでしょう。
自分次第でビジネスの幅を広げることができる
独立すれば、自分の思うようなキャリア形成がしやすくなります。「専門分野の案件を多く獲得する」「既存顧客だけでなく、新規顧客の獲得に力を入れる」など、自分の考えるビジネス展開ができるでしょう。
それによって、目の前の年収アップだけでなく、プロフェッショナルとしての成長にもつながります。さらなる年収アップの実現にもつながり、好循環も期待できます。
経営に関する具体的なアドバイスができるようになる
独立すれば弁護士としての法務だけではなく、経営にも携わらなければなりません。経営の実務経験は、経営に関する法律をより深く理解するための助けになるでしょう。
経営者視点と弁護士としての専門知識を持ち合わせることで、経営についての法律相談において、効果的な解決策の提案ができます。
定年退職がない
独立弁護士は雇われの弁護士と違い、定年退職がありません。本人が希望すれば、70代・80代になっても働き続けられます。
高齢になっても高い収入を望めるのは、独立のメリットです。
仕事を受ける相手や事件を選べる
独立弁護士は、得意分野や専門分野に絞った案件の受注も可能です。また利益につながらない依頼や、いい関係性を築きにくいクライアントからの依頼は断れるため、集中すべき業務に集中できるというメリットもあります。
独立のデメリット・注意点は?
独立にはメリットだけではなく、デメリットも存在します。具体的には以下の通りです。
- ・責任が重くなる
- ・積極的な情報収集をする必要がある
- ・軌道に乗るまでは年収が低い&初期費用がかかる
- ・上司や同僚など相談できる人が少なくなる
それぞれ解説します。
責任が重くなる
独立すれば、事務所経営におけるすべての責任を背負わなければなりません。
クライアントに対する業務責任だけでなく、財務や従業員の管理、利益の確保などの責任も生じます。
独立すれば自由度が増す分、責任も生じるということを念頭に置いておきましょう。
積極的な情報収集をする必要がある
独立すれば、大手事務所も含めた競合事務所と顧客を取り合うことになります。積極的な営業活動や情報の更新などを行わなければ、顧客に選ばれることはなかなか難しいでしょう。
情報収集は時間と労力を要求されるタスクですが、独立を成功させるためには必要不可欠です。
軌道に乗るまでは年収が低い&初期費用がかかる
先述の通り、事務所の開業にあたって、それなりの初期費用が必要です。また、独立直後は知名度が低いため、顧客獲得に難航しやすいのも事実です。
独立を成功させるには、財務計画をしっかりと立て、資金繰りを管理しなければなりません。
上司や同僚など相談できる人が少なくなる
弁護士業務のスムーズな進行においては、経験のある先輩弁護士の助言が有効であることが多々あります。
またちょっとしたことがすぐに相談できる環境は、円滑な業務進行だけでなく、精神衛生的にも非常に重要です。
独立すると一人で業務を進めなければならず、すぐに相談できる相手が身近にいなくなる点がデメリットといえます。
弁護士が独立までにするべき4つのステップ
弁護士が独立までにするべき4つのステップについてご紹介します。
1.開業資金の計画・調達
弁護士として独立するためには、まず開業資金の計画と調達が必要です。
前述した通り、開業にかかる費用は、事務機器の購入や事務所のレンタル、広告宣伝費、人件費、運転資金など多岐にわたるため、詳細な予算計画を立てることが重要です。
資金調達は、自己資金と銀行融資が主な方法ですが、地域によっては政府や地方自治体の補助金・助成金などを活用できる場合もあります。
2.顧客確保の土台作り
開業資金を準備して、独立開業できたとしても、顧客を確保しなければビジネスが立ち行かなくなります。
顧客確保の土台作りとしては、ウェブサイトやSNS、既存顧客からの紹介、無料相談の提供などが一般的です。
また、セミナーの開催や他の専門家との連携も有効な方法です。
既存顧客や知人からの紹介などは長く付き合える安定した顧客になり得るため、人とのつながりはとくに大切にすべき要素といえるでしょう。
3.取り扱う分野の確定
弁護士として独立する際には、取り扱う法律分野を明確にする必要があります。
専門分野を設定し、特化した知識と経験をアピールすることで、案件を獲得しやすくなるでしょう。
専門分野以外の案件については、他の弁護士や法律事務所と連携することで対応範囲を広げることも手段の1つです。
4.事務員など従業員採用
事務所の規模や業務量に応じて、事務員などの従業員が必要です。
従業員採用は業務効率の向上、弁護士業務に専念できる環境づくりにつながりますが、人件費や労務管理の負担も増加します。
そのため、開業当初は事務員を雇用せずに事務作業もすべて自分で担当し、経営が安定してから採用する流れが一般的といえるでしょう。
弁護士が独立後に年収を上げる3つのポイント
独立後に年収を上げるための3つのポイントを解説します。
集客方法を工夫する
弁護士としての独立後、収益を上げるためには効果的な集客が欠かせません。
しかし、飛び込み営業や弁護士としての品位がない勧誘は逆効果となる可能性があるため、注意しましょう。戦略的かつ効果的な集客方法を選ぶことが重要です。
開業当初など、十分に広告宣伝費をかけられない状況では、ウェブサイトの制作やSNSの活用が有効です。
ウェブサイトは事務所の専門性やサービス内容をわかりやすく伝えることができるため、受任件数の増加を期待できます。ユーザーの多いSNSを活用できれば事務所の認知度を上げることができるでしょう。
規模を拡大させる
年収を向上させるためには、事務所の移転や人員の拡充を含む事務所の規模拡大が重要です。
立地の良い場所へ移転し、人員を拡充させて業務処理能力を向上させることで、事務所としての売上が上がり、年収アップへとつながります。
第二、第三の事務所を開設や、 行政書士や税理士など他士業と協業する選択肢も考えられるでしょう。
専門性を磨いて差別化をする
専門性を磨き、事務所を差別化することは、競争力を保ちながら高い収益を上げ続けるために重要です。
特定の法律分野においての専門知識や経験を深め、「この種類の案件ならこの弁護士」といわれるような存在を目指しましょう。一過性ではなく、長続きする集客効果を得られるのも魅力です。
まとめ
弁護士として独立すれば、自分のペースで仕事が進められることに加え、専門分野の案件に集中する、新規市場を開拓していくなど、自分の裁量でビジネスを展開していくことが可能となります。
成功すれば、雇われ弁護士より、経済的にも時間的にも大きな余裕が生まれるはずです。
一方で、経営に関するすべての責任を背負わなければならないため、プレッシャーも増えるでしょう。従業員を雇っている場合は、本人やその家族の生活の責任も負うことになります。
また、相談できる人や同僚がいないため、自身で積極的に情報を取得する姿勢も求められます。
こうしたハードルを乗り越えることにやりがいを感じられる方は、独立も選択肢の1つでしょう。
また、独立後に成功を収めるためには集客方法の学習や、専門性の追求が必要不可欠です。独立のための下地を整える手段として、さまざまなノウハウをもつ弁護士事務所への転職も検討してもいいかもしれません。
裁量をもって働ける事務所であれば、独立に近い形かつ低リスクで働ける可能性もあります。
今後の方向性に迷っている方は、まずは転職エージェントに相談するとよいでしょう。一般的な転職だけでなく、独立も視野に入れた転職活動もサポートしてくれます。
- #弁護士の独立
- #開業弁護士
- #開業弁護士の年収
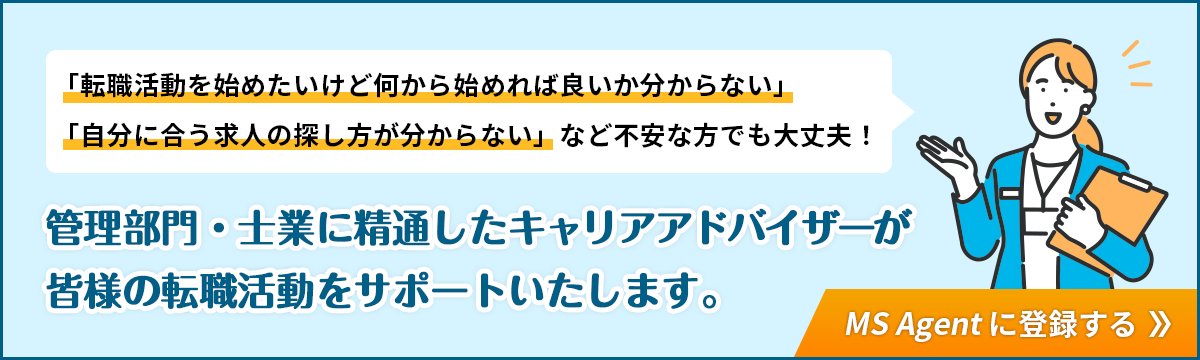
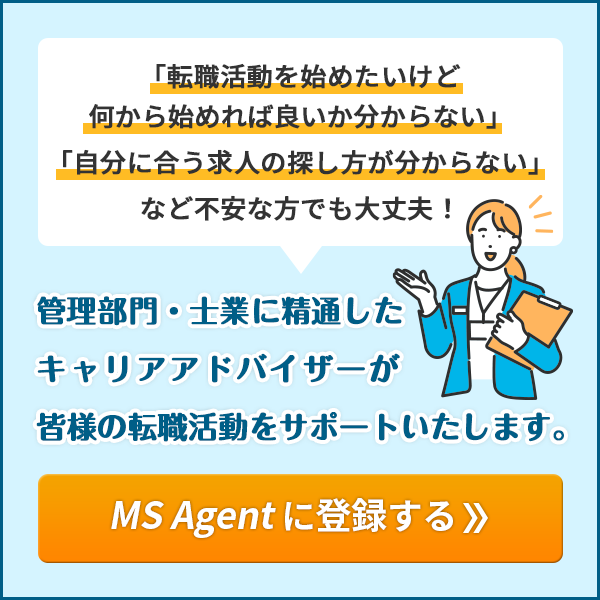
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、新卒でMS-Japanに入社。法律事務所や会計事務所、監査法人、社労士事務所、FAS系コンサルティングファームなどの士業領域の採用支援、及びその領域でのご転職を検討されている方の転職支援を行っています。
会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事
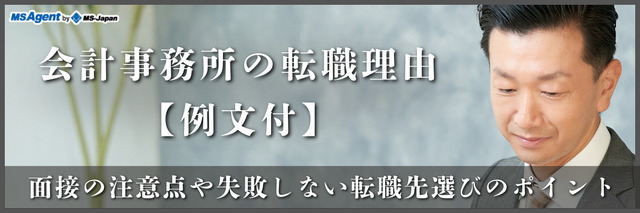
会計事務所の転職理由【例文付】面接の注意点や失敗しない転職先選びのポイント
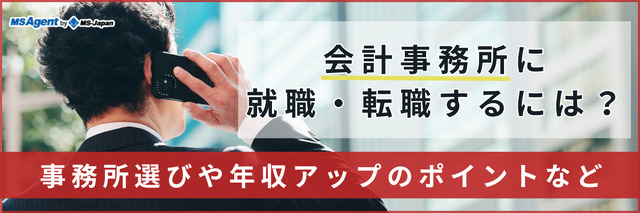
会計事務所に就職・転職するには?事務所選びや年収アップのポイントなど
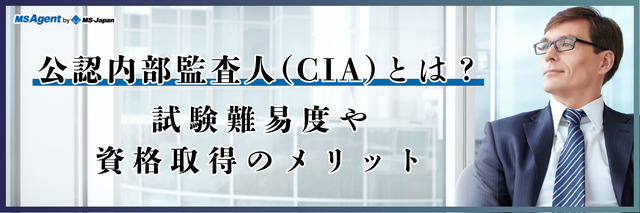
公認内部監査人(CIA)とは?試験難易度や資格取得のメリット
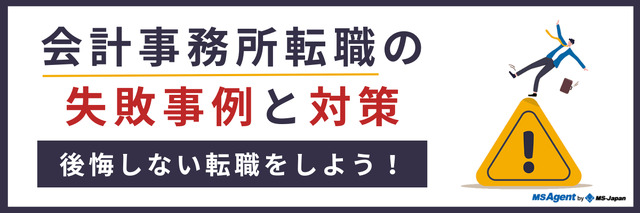
会計事務所転職の失敗事例と対策。後悔しない転職をしよう!
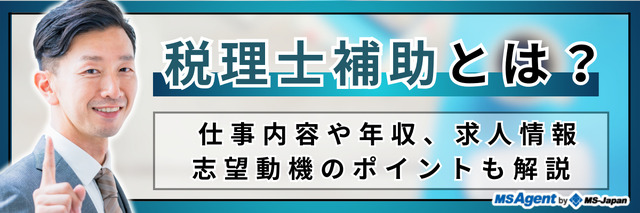
税理士補助とは? 仕事内容や年収、求人情報、志望動機のポイントも解説
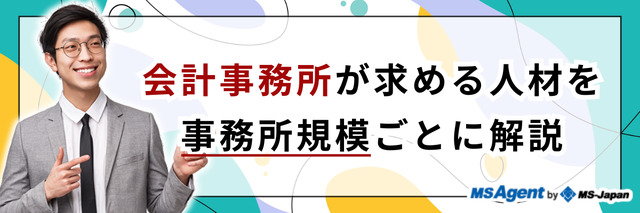
会計事務所が求める人材を事務所規模ごとに解説
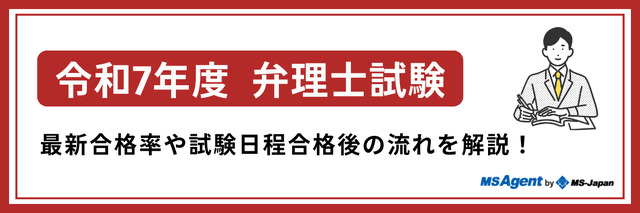
令和7年度弁理士試験|最新合格率や試験日程合格後の流れを解説!
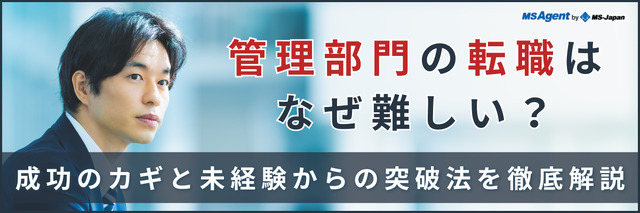
管理部門の転職はなぜ難しい?成功のカギと未経験からの突破法を徹底解説
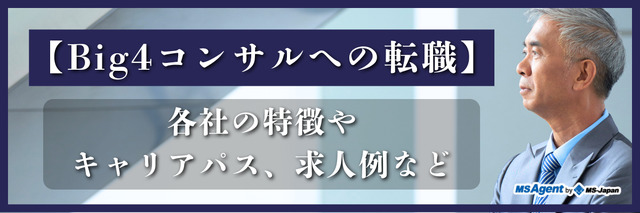
【Big4コンサルへの転職】各社の特徴やキャリアパス、求人例など
特集コンテンツ
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。