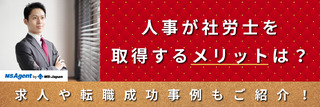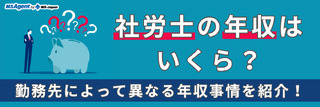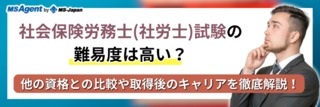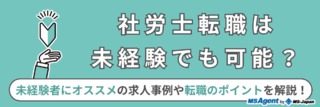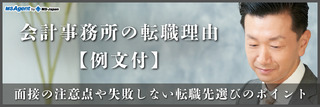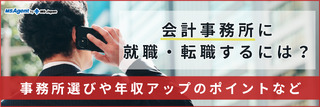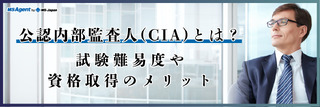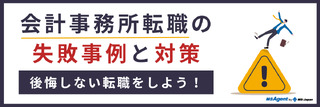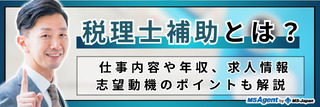社労士(社会保険労務士)とは?仕事内容や年収、試験難易度などを徹底解説!



国家資格である社会保険労務士は、実用性の高い人気資格ですが、難易度が高く合格率の低い試験です。
資格取得後は、社会保険労務士事務所や事業会社の人事・労務、独立開業など、幅広いキャリアが見込めるでしょう。
この記事では、社会保険労務士の働き方や年収事情、資格情報などを詳しく解説します。
社労士(社会保険労務士)とは
まずは、社労士の役割や仕事内容などの基礎知識を押さえておきましょう。
社労士の役割
社労士とは「社会保険労務士」の略で、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業が事業を行っていくには、お金や商品、従業員などさまざまな要素が必要ですが、社労士は従業員=人材に関わる専門家です。
社労士資格の目的は、社会保険労務士法第一条で「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」と定められています。
社労士の仕事は3種類
社労士の仕事は、主に1号業務・2号業務・3号業務の3種類に分けられます。このうち1号業務と2号業務は、社労士だけが行うことができる“独占業務”です。
それぞれの具体的な概要については、以下をご確認ください。
1号業務
社労士の1号業務とは、行政機関等へ提出する申請書類の作成や、作成した書類の提出手続きの代行等を指します。 具体的には、労働保険・社会保険の新規加入や脱退手続き、健康保険の出産手当金や傷病手当金などの給付申請手続き、各種助成金申請手続きなどが挙げられます。
2号業務
社労士の2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成です。就業規則や労働者名簿、賃金台帳など、企業が備えておく必要のあるさまざまな帳簿を作成します。
3号業務
社労士の3号業務とは、労務関係のコンサルティング業務です。事業における人事労務や社会保険に関する相談に応じたり、指導や助言を行ったりします。
3号業務は社労士の独占業務ではないため、資格保有者以外でも業務に従事することが可能です。
社労士の求人情報を確認したい方はコチラ

社労士の求人情報
社労士資格を保有している方向けの求人一覧ページです。上場企業の人事労務や社労士事務所の求人など企業・事務所両方の求人を確認できます。
またサイト上に公開されている求人はごく一部の求人です。会員登録することでより多くの求人をご確認することが可能です。

社会保険労務士事務所の求人情報
国内最大級の社会保険労務士事務所に関する求人情報を保有している弊社では、これから社会保険労務士事務所で働きたい方や他の社会保険労務士事務所に転職して活躍したい方などのご要望に応じて求人など数多くご用意しております。
弊社のみが扱っている求人も多いため、ぜひご確認ください。
社労士の詳しい仕事内容
社労士業務の中でも割合の大きい「労働社会保険手続」、「労務管理の相談指導」、「年金相談」、「紛争解決手続代理」について、掘り下げて解説していきましょう。
労働社会保険手続
企業で働くにあたり、労働社会保険(労働保険・社会保険)への適切な加入は、従業員が安心して働くためには必要不可欠です。
例えば、就業中の事故により休業期間が発生した際の治療費や休業補償の申請や健康保険や年金保険の手続きなどを社労士が代行することで、適正に処理され、安心して働くことのできる環境が作られています。
労働社会保険手続は1号業務に該当します。
労務管理の相談指導
社労士は、人事労務管理の専門家として、労働時間の管理や従業員の採用・育成に関する相談指導を行います。
就業規則の作成・見直しや、賃金制度構築のアドバイスなど、従業員と企業が良好な労使関係を築くためのコンサルティングです。
労務管理の相談指導は、3号業務に該当します。
年金相談
国民年金は、原則すべての人が加入し、年金の支払いや受給が行われる制度です。しかし、年金制度は日々変化しているため、変化に対応できなければ、受けられるはずだった年金が受けられずに、損をしてしまうケースがあります。
従業員の権利を守るために、社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、年金に関しての相談を受けています。
年金相談も3号業務に該当します。
紛争解決手続代理(ADR)
社労士は、全国社会保険労務士会連合会による特別研修を受講し、専門試験に合格することで「特定社会保険労務士」として登録することが可能です。
特定社会保険労務士になると、「労働紛争に伴う裁判外紛争手続きの代理業務」が独占業務に追加されます。
紛争解決手続代理とは、労働の中で発生したトラブル、会社と従業員とのトラブルなどに対して、労務管理の専門知識を活かして、第三者の立場から解決を図ることです。
裁判が必要となった場合は費用も時間もかかりますが、特定社労士によるADR代理業務で、裁判をせずに「話し合い」によって仲裁を行い、紛争解決の手続きを行います。
社労士の就職・転職先
社労士の就職・転職先には、「社労士事務所」「企業の人事・総務」、「社労士事務所の開業」が挙げられます。各就職・転職先について詳しく見ていきましょう。
社労士事務所
社労士の最も代表的な就職・転職先が「社労士事務所」です。
個人や企業など様々なクライアントの人事・総務に関する相談や依頼を受けています。代表的な選択肢ではありますが、実は求人数は少なく、社労士の登録人数が増えている 昨今、比較的難易度が高い傾向です。
社労士として専門的に働くことができるため、最も効率良く社労士としてのスキルや経験を積むことができます。将来的に社労士事務所を開業したいと考えている方に最適なキャリアパスです。
企業の人事・総務
近年では、企業の人事・総務部門で「勤務社労士」として働く選択肢もあります。
勤務社労士を雇う事によって、企業は外部の社労士にコンサルティングを依頼せず、労務問題を解決することができるため、近年需要が高まっている就職・転職先です。
「勤務社労士」というポジションではなくても、社労士資格や経験は企業の人事・総務において評価されるため、人事・総務への就職・転職で有利に働くでしょう。
社労士が企業の人事・総務として働くメリットは、収入の安定や福利厚生面が挙げられます。また、社労士事務所よりも求人数が多いため、希望の条件や環境で勤務できる可能性が高いでしょう。
しかし、勤務社労士としての採用でない場合は、社労士以外の業務も行う必要があります。社労士としての経験を積みたいという方は、物足りない・スキルアップできないと感じてしまう可能性があるため、入社前に細かい業務内容を確認しましょう。
社労士事務所の開業
社労士事務所や企業で社労士経験を積んだ後は、自身の事務所を持ち、「開業社労士」として独立することもできます。しかし、独立開業するためには、クライアントの新規開拓が重要です。
そのため、社労士としての実力だけではなく、営業力や経営力も必要も求められます。
社労士事務所を開業することのメリットは、自分の裁量で働けることです。また、努力した分だけ収入につながるため、事務所を開業し成功した場合は社労士事務所や企業に勤務するよりも高収入を得られます。
しかし、クライアント開拓が上手くいかなかった場合は収入を得ることができないため、開業する際は下準備が重要です。
【就職・転職先別/年齢別 】社労士の年収
続いては、社労士の年収に注目してみましょう。 ここでは「就職・転職先別」と「性別・年齢別」のカテゴリごとに年収相場を解説しながら、士業・管理部門特化型転職エージェント「MS Agent」における社労士のオファー年収もあわせてご紹介します。
【就職・転職先別】社労士の年収
「社労士事務所所属」「企業勤務」「開業社労士」のおおよその年収は以下の通りです。
| 就職・転職先 | 年収目安 |
|---|---|
| 社労士事務所所属 | 500万円~700万円 |
| 企業勤務 | 500万円~700万円 |
| 開業社労士 | 100万円~1,000万円 |
それぞれの見解について、以下で詳しく見ていきましょう。
社労士事務所所属
社労士事務所に所属している社労士の年収は、主に階級によって決定されます。
「アソシエイト」の段階の年収は500万円程度とあまり高年収は期待できません。ただし、一般企業でいう役員レベルの「パートナー」にキャリアアップすると、高額な報酬を得られる傾向があります。
企業勤務
一般企業では「社労士資格で大幅に年収が上がる」ケースは少なく、社労士資格を活かして企業の利益に貢献し、評価を高めることで年収が上がるケースが多いです。
また、企業規模によっても年収上限が異なり、大手企業に勤務すれば高年収も期待できます。
開業社労士
開業社労士は0から顧客獲得を行う必要があるため、クライアント数によって年収が大きく左右されます。
また、社労士の契約には、顧客企業と1回のみの契約を結ぶ「単発型」と、顧問契約を締結して業務を受注する「継続型」の2種類があり、安定した収入を得るためには、毎月必ず収入が発生する「継続型」の企業を増やすことがポイントです。
【性別・年齢別】社労士の年収
次に、社労士平均年収を性別・年齢別に見ていきましょう。
少し古いデータではありますが、厚生労働省の令和元年賃金構造基本統計調査では、社労士の男女別平均年収を以下の通り発表しています。
| 年齢 | 社会保険労務士(男) | 社会保険労務士(女) |
|---|---|---|
| 20~24歳 | - | - |
| 25~29歳 | - | - |
| 30~34歳 | 557万円 | 277万円 |
| 35~39歳 | 447万円 | 453万円 |
| 40~44歳 | 493万円 | 437万円 |
| 45~49歳 | 541万円 | 402万円 |
| 50~54歳 | - | 497万円 |
| 55~59歳 | - | 543万円 |
| 60~64歳 | 834万円 | - |
| 65~69歳 | - | - |
| 70歳 | 345万円 | 318万円 |
| 全体 | 515万円 | 434万円 |
参考:令和元年賃金構造基本統計調査
上記の表を見ると、男性の社労士は30代~40代のうちは500万円程度の年収相場ですが、60歳を超えると急激に上がっていることがわかります。
一方、女性の社労士の場合は30代のうちは300万円弱の年収相場ですが、30代以降は男性社労士の相場とほとんど変わりません。なお、社労士として活躍している女性は年々増加傾向にあり、その背景にはこうした年収の高さが大きく関係していると考えられます。
上記表の「-」は、令和元年賃金構造基本統計調査で該当年齢層の調査対象がいなかったことを意味します。
調査対象となる社会保険労務士の母数が少ないことから、翌年以降は、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」として、証券アナリスト、アクチュアリー、経営コンサルタントと合算されています。
【年齢別】社労士の転職決定年収・中央値
これから社労士資格の取得や、社労士としての転職を考えている方の中には、「転職直後の年収」が気になっている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、2023年7月~2024年6月の1年間で、MS-Japanの転職エージェントサービスMS Agentを利用して転職された社労士のオファー年収をご紹介します。
| 年齢 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| ~29歳 | 412万円 | 390万円 |
| 30~34歳 | 454万円 | 450万円 |
| 35~39歳 | 471万円 | 450万円 |
| 40~44歳 | 515万円 | 500万円 |
| 45歳~ | 591万円 | 565万円 |
| 全体 | 489万円 | 500万円 |
※オファー年収は月額給与及び定期的に支給される賞与の合計額であり、別途支給される時間外手当や決算賞与等の変動要素がある金額に関しては含まれておりません。
上記の「オファー年収」と前述の「年代別の平均年収」を比較してみると、全体的に大きな差はみられません。
ただし、40代・50代の年収はMS-Japanのオファー年収の方が高めの水準となっていることから、MS-Japanにおいては好条件で転職を遂げた社労士の方が多いことがうかがえます。
社労士のやりがい
ここでは、社労士のやりがいを3点紹介します。
困っている労働者をサポートできる
社労士の仕事は、困っている労働者を助ける事です。企業の経営者だけでなく、現場で働いている労働者の手助けをすることもできます。
特に勤務中の怪我や会社の倒産など、労働者が困っている場面で活躍できるため、誰かの助けになる仕事がしたいと考えている方はやりがいを感じられるでしょう。
企業の経営に関われる
企業が経営を成功させるためには、労働者が十分な実力を発揮できる環境を創ることが重要です。社労士は経営者とともに、労働環境改善に向けて働きかけます。そのため、社労士は企業の経営に大きく関わっていると言えるでしょう。
高収入が期待できる
社労士は独立して事務所を開業した場合、努力次第で高収入を得ることができます。
また、誰かの助けになる仕事を通して、多くの顧客を獲得し、リピーターが付くことで大きなやりがいを感じることができるでしょう。
社労士に向いている人の特徴
次に、社労士に向いている人の特徴をまとめました。
数字に強い
社労士の業務は、労働者一人ひとりの健康保険料や雇用保険・災害保険の給付、年金支給額などの計算、帳簿の作成や記入など、細かな数字を扱うものがほとんどです。
これらの業務でミスが起こると、クライアント企業やそこで働く労働者に対して、大きな不利益を発生させてしまうでしょう。そのため、社労士は数字に強く、正確性の高い業務が遂行できる人が向いています。
コミュニケーション能力が高い
社労士の業務は細かな計算だけではありません。労務管理の相談指導や年金相談を含む労務関係のコンサルティング業務では、クライアントとの密なコミュニケーションが不可欠です。
クライアントが納得のいく提案をするスキルだけでなく、クライアントが抱える問題を聞き取る傾聴力も求められます。
また、開業社労士の場合も、自身でクライアントを開拓する必要があり、営業力が必須だと言えるでしょう。
地道な作業が得意
社労士は、困っている労働者をサポートし、感謝の言葉をもらえる場面も多い職種です。
一方で、日々従事する実務は、計算や帳簿作成など、比較的地味な作業が多いと言えるでしょう。
地味な作業にコツコツと取り組める人やルーティンワークが苦にならない人は、社労士が向いていると考えられます。
社労士の将来性は?
社労士の将来性を考える上で、昨今活躍の場を広げているAIは切り離せません。
他職種でも考えられるように、社労士の仕事の中でも事務作業や申請業務など、ルーティーンワークとされている部分は、AIに置き換えられていくといえるでしょう。
しかし、コロナ禍に発生した助成金などのように、社会情勢の影響を受けて発生した問題やイレギュラーな問題はAIで対応できません。
また、近年における働き方の多様化の影響を受け、3号業務である労務関係のコンサルティング業務の需要が増えています。幅広い知識と経験を根拠としたコンサルティングが求められるため、社労士の仕事が全てAIにとって変わることはないでしょう。
社労士が女性におすすめの理由
会計士や弁護士など、他の士業と比較して、社労士は女性が活躍しやすい職種であると言われています。その理由は以下の通りです。
他の士業と比較して女性の割合が多い
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 61.2% | 38.8% |
| 弁護士 | 71.6% | 29.4% |
| 公認会計士 | 77.70% | 22.5% |
上記表を見ると、社労士の女性比率は弁護士・公認会計士と比較して非常に高いことが分かります。
また、社労士の女性比率は年々大きくなっているため、今後も女性比率は高くなると想定されるでしょう。
結婚、子育てなどと両立しやすい
社労士事務所は、企業の労働環境改善という職務上、出産・子育てなどによる休職や正社員以外の勤務形態など、女性が安心して働ける環境が整っている事務所が多い傾向です。
また、産前産後休業・育児休業などの経験がある場合は、当事者としての目線からアドバイスができるでしょう。
子育てしながらでもキャリアアップが出来る為、女性が続けやすい仕事であるといえます。
女性社労士が重宝される
社労士の業務は、数字を扱う事務作業がメインであり、力仕事や体力勝負の仕事ではないため、女性も活躍しやすい仕事だと言えます。
また、昨今増加している女性の働き方や労働問題等を扱う場合、女性社労士の方が「話しやすい」「当事者の立場で話を聞いてもらえる」と考えるクライアントが多く、女性社労士のニーズが増加していると考えられます。
社労士になるには?社労士試験について
社労士試験の受験資格
社労士試験の受験資格は以下の通りで、いずれかに該当している必要があります。
| 受験資格 | 詳細 |
|---|---|
| 学歴 | 一般的な大学や短期大学、専門学校など所定の学校を卒業している |
| 実務経験 |
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員または従業者 ・国または地方公共団体の公務員 ・日本郵政公社の役員または職員 ・社会保険労務士または弁護士の補助者 など ※実務期間に関する条件あり |
| 国家資格合格 |
・司法試験予備試験 ・税理士試験 ・公認会計士試験 ・弁理士試験 など |
社労士試験の科目
社労士試験において出題される科目は以下の通りです。
| 試験科目 | 詳細 |
|---|---|
| 労働保険科目 |
・労働基準法 ・労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・労働者の保険料の徴収等に関する法律 ・労務管理その他の労働に関する一般常識 ・雇用保険法 |
| 社会保険関係科目 |
・社会保険に関する一般常識 ・健康保険法 ・厚生年金保険法 ・国民年金法 |
上記の10科目について科目ごとに合格基準が設定されるため、ひとつひとつの科目についてしっかりと知識を深めたうえで試験に挑むことが求められます。また、科目合格制度がないため、1度の受験で全ての科目に合格する必要があります。
合格後は2年以上の実務経験、または事務指定講習の修了により社労士として登録することが可能です。
社労士試験の難易度・合格率
社労士試験は「難関資格」として有名です。ここでは合格率や目安となる勉強時間、独学でも合格可能かどうかなどに注目し、社労士の具体的な難易度について紐解いていきましょう。
社労士試験の合格率
まずは、過去5年間における社労士試験の合格率に注目してみましょう。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 令和6年度 | 6.9% |
| 令和5年度 | 6.4% |
| 令和4年度 | 5.3% |
| 令和3年度 | 7.9% |
| 令和2年度 | 6.4% |
年によって多少の増減はあるものの、平均すると約6%~7%で推移しています。10科目という非常に多くの科目が出題され、各科目において深い知識が求められることや、選択式試験に苦戦する受験者が多いことが低い合格率につながっている印象です。
また、出題科目の中には毎年のように法改正が行われるものもあるため、1度勉強して終わりではなく、情報のアップデートが求められます。
社労士試験の勉強時間
社労士試験合格のために必要な平均勉強時間は、1,000時間以上といわれています。 1日3時間のペースで毎日勉強しても333日、およそ1年程度の期間がかかります。
また、仕事をしながら、学校に通いながらなど、1日の勉強時間が十分に確保できない場合はさらに長い期間がかかる可能性があるでしょう。
社労士試験は独学でも合格できる?
社労士資格を目指している方の中には、独学での勉強を考えている方も多いのではないでしょうか。
実際に、これまで社労士試験合格者の中には独学で合格した方もいます。しかし、独学で合格した方の多くは、人事・労務などの実務経験や法律の知識を有している方がほとんどです。
社労士試験の合格率は平均6%台と難易度が非常に高いため、全くの未経験から独学で合格できる可能性は低いとされています。独学での勉強が不安な場合は、通学講座や通信講座などを利用しましょう。
社労士資格取得のメリットは?
社労士資格は難関な国家資格の1つであるため、試験合格は容易ではありませんが、資格を取得することでメリットも多くあります。
1つ目は、社労士事務所の開業で高収入を期待できることです。
「社労士の就職先」で先述した通り、社労士事務所を開業し、クライアントの獲得や事務所の経営が上手くいけば高年収が期待できます。また、会社にとらわれずに業務が出来ることも開業することのメリットです。
2つ目は、自分自身の労務環境を整えられることです。
社労士の役割はクライアント企業の労務を守ることですが、勤務社労士は自身も企業や事務所に雇われている立場です。そのため、労務関連法律の知識は、自分自身を守ることにもつながります。
3つ目は、就職・転職に有利になることです。企業の人事・総務部門への就職、転職に有利になるだけでなく、管理部門全般でも評価の対象となります。
社労士とのWライセンスがおすすめの資格
社労士資格は単体でも需要はありますが、社労士資格と合わせて別の資格を取得し、ダブルライセンスを得ることで他者との差別化を図れます。以下の8つが社労士とのダブルライセンスで相性が良い資格です。
ファイナンシャルプランナー
社労士のダブルライセンスとして相性がいい資格のひとつにFP(ファイナンシャルプランナー)があります。
ファイナンシャルプランナーを取得することにより、個人や法人の財務プランニングに関する専門知識を得ることができます。
労働法や社会保険制度に関する知識を得ることができる社労士とファイナンシャルプランナーのダブルライセンスを取得することで、顧客に対して総合的なアドバイスを行うことが可能です。
行政書士
社労士と行政書士は、業務上の相性がとても良いと言われています。
例えば、会社を設立するための手続きがあげられます。行政書士は、会社設立時に必要となる許認可申請や定款の作成などを行い、社労士は、社会保険関係の手続きや労働保険関係の手続き、労務管理などを担当します。
通常、それぞれ異なる専門家に依頼することになりますが、ダブルライセンスを取得していれば、ワンストップで業務に対応することができるのです。
このように、担当できない分野を互いに補い合えるのが社会保険労務士と行政書士で、仕事の選択肢を増やすという意味でも効果的と言えるでしょう。
税理士
「税務の専門家」である税理士と「年金や公的保険、労働法に関する専門家」である社労士の両方を取得することで、税金・労務・社会保険をワンストップで対応できるようになります。
また、日本国内の税理士人口は令和6年時点で8万人を超え、競争が激化しています。
社労士と税理士のダブルライセンスを取得することで、生き残りを図るための強力な武器になると考えられるでしょう。
社労士有資格者の転職市場
社労士資格を歓迎要件とする求人は多く、アピールポイントとなるでしょう。社労士事務所だけではなく、企業の人事・総務、他士業事務所の求人でも評価されます。
しかし、特に企業の人事・総務の転職市場では、資格だけでなく実務経験も重視されるケースが多い印象です。
社労士資格だけでなく、コミュニケーション力などのヒューマンスキルや、応募先の仕事内容と関連するスキルなど、+αのスキルをアピールすることが重要です。
社労士のおすすめ求人事例
ここでは、MS-Japanが取り扱っている社労士求人の事例をいくつかご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
社会保険労務士法人の労務コンサル担当求人!
| 仕事内容 |
|
・労務コンサルティング ・就業規則・社内規程の策定 ・労務監査 |
| 必要な経験・能力 |
|
・社労士有資格者優遇(資格取得を目指している方も応募可能) ・人事/労務に知見がある方 ・コミュニケーション力の高い方 |
| 想定年収 |
| 350万円~600万円 |
プレイングマネージャー候補の即戦力社労士求人!
| 仕事内容 |
|
・給与計算 ・労働保険、社会保険手続 ・就業規則作成 |
| 必要な経験・能力 |
|
・社会保険労務士資格者 ・社会保険労務士事務所経験 |
| 想定年収 |
| 450万円~600万円 |
マスコミ・広告業界の人事総務求人!
| 仕事内容 |
|
・労務管理と人事規程の整備 ・給与計算や社会保険手続きなどの労務業務 |
| 必要な経験・能力 |
|
<必須> ・労務もしくは制度のご経験 <歓迎> ・社労士資格取得者 |
| 想定年収 |
| 450万円~550万円 |
老舗住宅建材商社の労務求人!
| 仕事内容 |
|
・給与/社会保険関連業務 ・労務相談業務/人事既定の運用管理 ・社宅手続きなど福利厚生関連業務 |
| 必要な経験・能力 |
|
<歓迎> ・労務業務の実務経験 ・社会保険労務士資格 |
| 想定年収 |
| 413万円~530万円 |
まとめ
社労士資格を取得すれば、就職・転職でアピールポイントにはなりますが、資格だけで高年収を得るのはなかなか厳しいといえるでしょう。
また、社会保険労務士事務所と企業では、一般的に企業の方が年収は高いケースが多いですが、社労士として独立開業を目指したい方、プロフェッショナルなスキルを高めたい方は、社会保険労務士事務所でキャリアを積むことをおすすめします。
社労士資格を活かした転職活動は、弊社MS-Japanが運営する管理部門・士業特化型転職エージェント「MS Agent」にご相談ください。社労士事務所はもちろん、企業の人・労務・総務分野の求人も豊富に取り扱っています。
- #社労士
- #年収
- #仕事内容
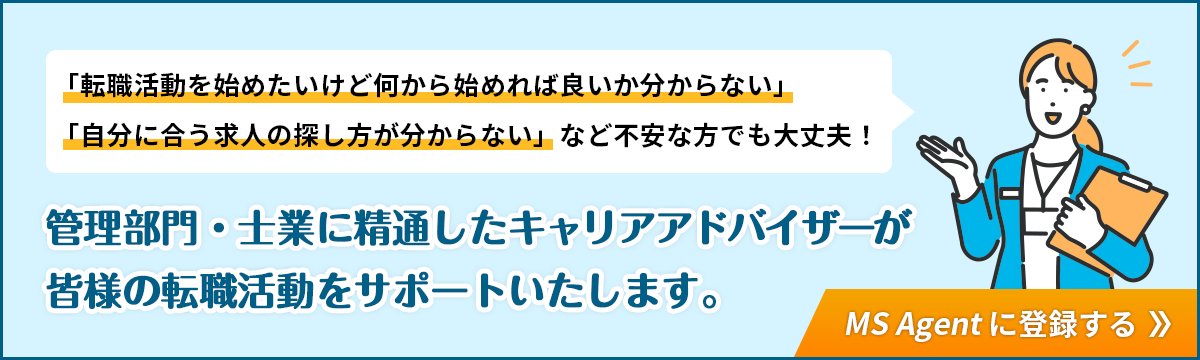
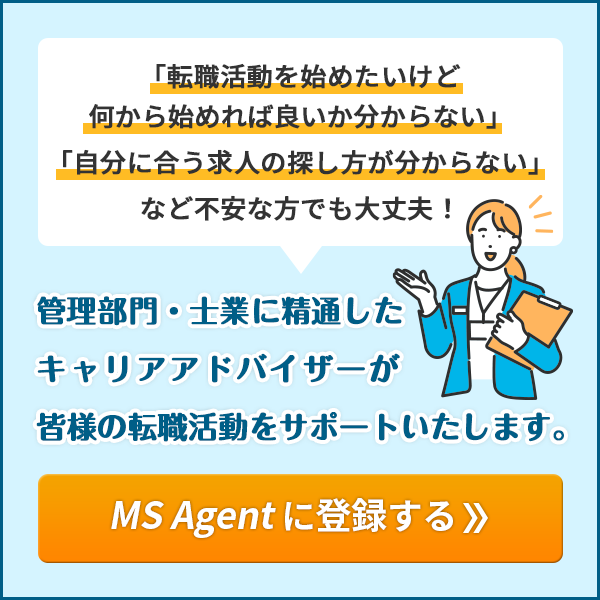
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、新卒でMS-Japanへ入社。企業側を支援するリクルーティングアドバイザーとして約6年間IPO準備企業~大手企業まで計1,000社以上をご支援。
女性リクルーティングアドバイザーとして最年少ユニットリーダーを経験の後、2019年には【転職する際相談したいRAランキング】で全社2位獲得。
2021年~キャリアアドバイザーへ異動し、現在はチーフキャリアアドバイザーとして約400名以上ご支援実績がございます。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 法律・特許事務所 ・ 役員・その他 ・ 社会保険労務士事務所 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事
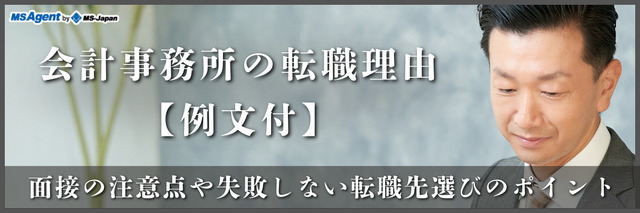
会計事務所の転職理由【例文付】面接の注意点や失敗しない転職先選びのポイント
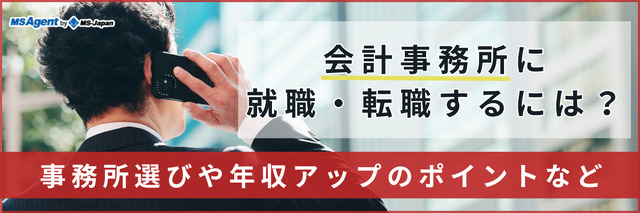
会計事務所に就職・転職するには?事務所選びや年収アップのポイントなど
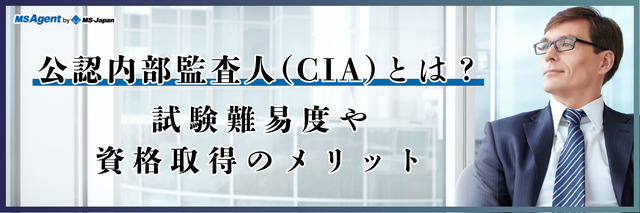
公認内部監査人(CIA)とは?試験難易度や資格取得のメリット
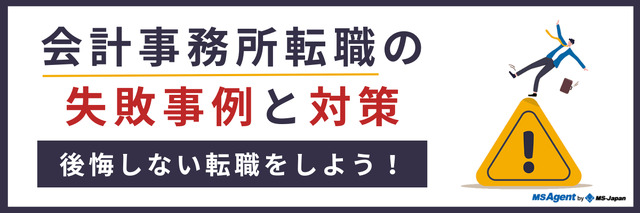
会計事務所転職の失敗事例と対策。後悔しない転職をしよう!
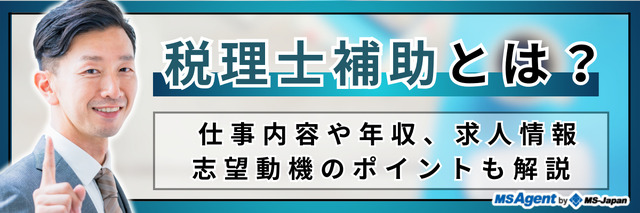
税理士補助とは? 仕事内容や年収、求人情報、志望動機のポイントも解説
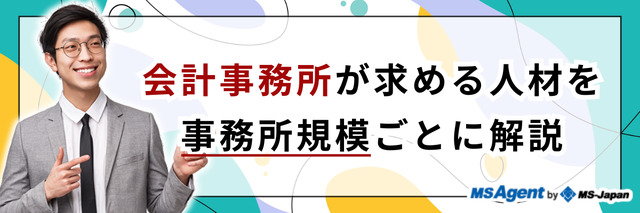
会計事務所が求める人材を事務所規模ごとに解説
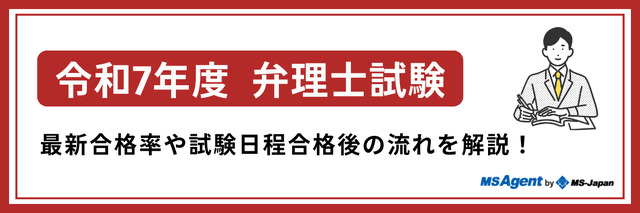
令和7年度弁理士試験|最新合格率や試験日程合格後の流れを解説!
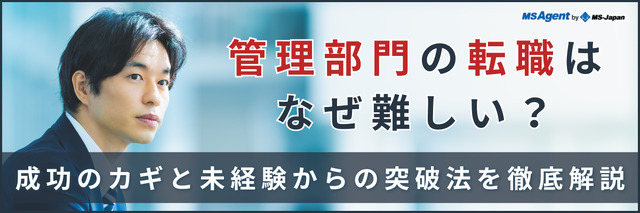
管理部門の転職はなぜ難しい?成功のカギと未経験からの突破法を徹底解説
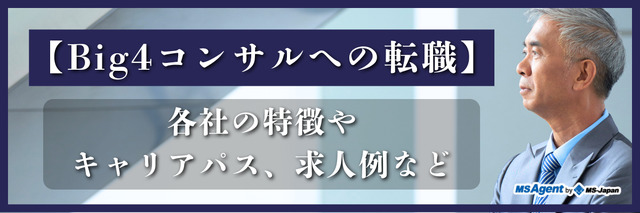
【Big4コンサルへの転職】各社の特徴やキャリアパス、求人例など
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。