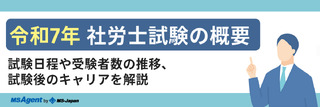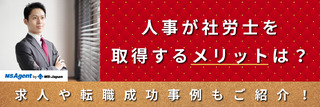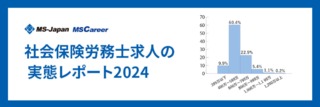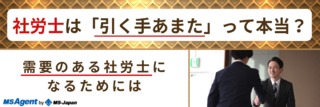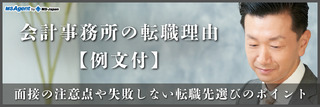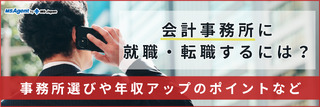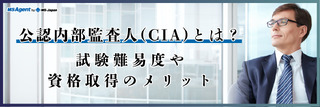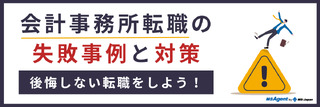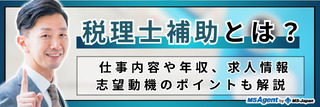令和7年社労士試験の概要 | 試験日程や受験者数の推移、試験後のキャリアを解説
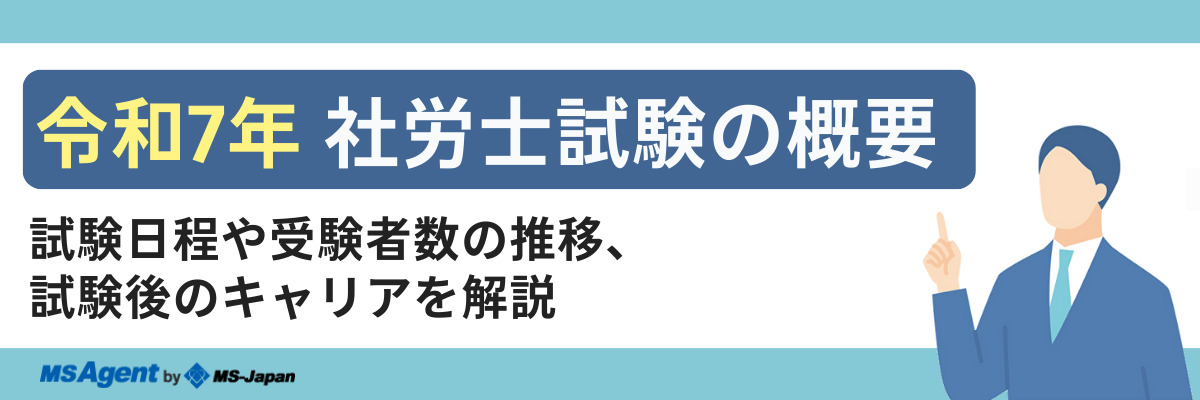
8月24日(日)に第57回社会保険労務士試験が実施されました。
本記事では令和7年の社労士試験の概要と過去の試験結果、合格後のキャリアについてまとめました。
今年受験された方だけではなく、来年以降の受験をお考えの方もぜひ参考にしてください。
社労士(社会保険労務士)とは?
社会保険労務士(通称:社労士)は、労働・社会保険の問題に関する専門家です。
独占業務として、社会保険労務士法に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成することができる国家資格です。
社労士は、労働者の権利保護や企業の人事・労務管理を支える重要な役割を担います。
具体的な業務は以下の通りです。
- ・給与計算、労働災害における申請などの事務手続
- ・社会保険(健康保険・厚生年金等)における私傷病、出産、死亡等に関する申請などの事務手続
- ・労働保険(労災保険・雇用保険)における申請などの事務手続
- ・労働者名簿および賃金台帳など法定帳簿の作成、就業規則等の作成・改訂など
また、社労士は、個人からの依頼による年金に伴う相談・申請代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割等)なども行います。
これらの業務を通じて、社労士は労働者と企業の間に立ち、公正な立場で誠実に業務を行い、労働環境の改善や労働者の権利保護に貢献しています。
あわせて読みたい
社労士試験とは?受験資格や試験科目、合格基準など
社労士試験の受験資格
社労士試験には受験資格があり、「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つのうち、いずれか1つを満たす必要があります。
学歴による受験資格
- ・大学、短期大学を卒業した者
- ・大学(短期大学を除く)における所定の単位を修得した者
- ・専門学校卒業者 など
実務経験による受験資格
- ・労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員または従業者
- ・国または地方公共団体の公務員等
- ・日本郵政公社の役員または職員 など
厚生労働大臣の認めた国家試験合格による受験資格
- ・社労士試験以外の国家試験合格者
- ・司法試験予備試験等の合格者
- ・行政書士試験の合格者
参考:受験資格について|社会保険労務士試験オフィシャルサイト
社労士試験の試験科目と合格基準
社労士試験は以下の科目/配点にて行われます。
| 試験科目 | 選択式(配点) | 択一式(配点) |
|---|---|---|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労働者災害補償保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 雇用保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
合格基準点は、選択式試験および択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めます。
一定の合格点はなく、合格発表日にその年の合格基準点が公表されるため、受験される方は注意が必要です。
なお、令和6年度の社労士試験合格基準は、次の2つの条件を満たした場合に合格となりました。
①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)である者
②択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上である者
上記の合格基準を得点率に換算すると、選択式試験では62.5%(25点/40点)、択一式試験では約62.9%(44点/70点)となります。
しかし、総得点だけではなく、各科目にも合格基準が定められているため、受験者は全科目偏りなく学習する必要があります。
令和7年社労士試験の日程について
令和7年の第57回社労士試験は以下の日程で行われました。
| 内容 | 日程 |
|---|---|
| 申し込み | 令和7年4月14日(月) ~5月31日(土) |
| 試験日 | 令和7年8月24日(日) |
| 合格発表 | 令和7年10月1日(水) |
令和8年の第58回社労士試験については、まだ日程が公開されていません。
試験の申込期間は、例年4月中旬~5月31日であるため、次回の受験を検討している場合は、社会保険労務士オフィシャルサイトを随時確認しましょう。
過去10年間の社労士試験の結果
過去10年間における社労士試験の受験者数や合格率など推移は以下の通りです。
社労士試験の受験申込者と受験者数の推移
受験者数は平成27年から緩やかに減少しており、新型コロナウイルスの影響が大きかった令和2年は直近10年間で最も少ない34,845人でした。
その後は徐々に回復傾向にあり、令和6年には10年間で最大の43,174名となりました。
社労士試験の合格者数と合格率推移
社労士試験の過去10年間における合格率の平均は6.0%です。
平成27年・28年の合格率が低い理由は、表外の情報になりますが、平成26年の合格率が9.3%と例年と比べ非常に高く、その後、2回で合格者数の調整をするために、試験問題の難易度を調整した可能性があるといわれています。
令和4年に合格者数・合格率ともに落ち込んだものの、直近2年間は増加傾向にあります。
年齢/職業/性別から見る合格者の特徴
年齢別にみると、最多は35~39歳の16.4%で、30~40代が全体の6割以上を占めています。
職業別で比較すると、会社員が59.9%と最多となっており、働きながら資格取得を目指す人が多いことが分かります。
男女別の割合を見てみると、女性が38.9%と合格者の3人に1人が女性であることが分かります。
その他の国家資格における合格者の女性比率は、令和6年の公認会計士試験が22.4%、税理士試験は30.6%であることから、社労士は他の士業と比較して女性が多いと言えるでしょう。
参考:過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合|社会保険労務士試験オフィシャルサイト
社労士試験合格後にするべきこと
社労士試験合格後、社労士として働くためには、「2年以上の実務経験」または「事務指定講習を修了」し、全国社会保険労務士会連合会の社労士名簿に登録する必要があります。
実務経験の期間は、試験合格前後どちらでも構いません。
事務指定講習とは、例年2月〜5月にかけて実施される講習で、通信指導課程と面接指導課程(eラーニング講習)を組み合わせて実施されます。
社労士登録にかかる費用
事務指定講習の受講料は77,000円(税込)です。
また、全国社会保険労務士連合会に登録するための登録手数料と登録免許税は、それぞれ全国一律で30,000円となっています。
このほかにも、入会金や年会費が発生しますが、働き方(独立開業型・勤務型)や、登録する地域によって費用が異なります。
目安として、合格後は20万円以上かかると見ておいたほうがよいでしょう。
社労士合格後のキャリア
社労士事務所
社労士資格を活かすキャリアとして、最も一般的な選択肢が社労士事務所です。
主な業務として、顧問先企業の社会保険手続きや簡単な労務相談などを行います。
顧問先となる企業は、中小・ベンチャー企業が中心ですが、数十人規模の事務所で幹部クラスになれば、大手企業の労務担当者とやりとりすることもあるでしょう。
人事・労務制度に関するコンサルティングやセミナーなどを行うこともあります。
一般企業の人事・総務部
社労士資格取得者は、一般企業の人事・総務部で「勤務社労士」として働くことも可能です。
社会保険・労務分野の専門家として、一般企業からのニーズも高い傾向にあります。
顧問契約ではなく、従業員として雇用されることで、企業の組織文化や働き方の改善に対して直接的に関わり、企業成長に貢献できるため、社労士事務所では味わえないやりがいも多いでしょう。
社労士として人事・総務部に所属すれば、昇格の可能性も高まり、業務の幅も広がるでしょう。
社労士として独立開業
社労士資格を活かして事務所を設立し、独立開業することも可能です。
独立開業には、社労士としての知識・スキルだけでなく、営業力も求められます。
営業活動が苦手で、顧問先を確保できない場合、単発的な相談や依頼が中心となるため、収入が不安定になる可能性が高いでしょう。
ただ単に、聞かれたことに答えたり、説明したりするだけでは、企業の経営者の心を掴むことはできません。
収益に繋がるような実践的アドバイスができると、大きな強みとなるでしょう。
あわせて読みたい
社労士試験合格後の転職活動は早めがカギ!
試験合格後に転職を検討される方は、できるだけ早い段階で転職活動や求人応募を始めることがおすすめです。
弊社MS-Japanは、人事・労務などの管理部門と、社労士を含む士業に特化した転職エージェントとして35年以上の実績があります。
社労士資格を活かせる求人の紹介はもちろん、応募書類の添削や面接対策、キャリアアドバイザーによるキャリアカウンセリングも行っているため、転職活動に不安がある方はお気軽にご相談ください。
- #社労士
- #社会保険労務士
- #社労士試験
- #転職
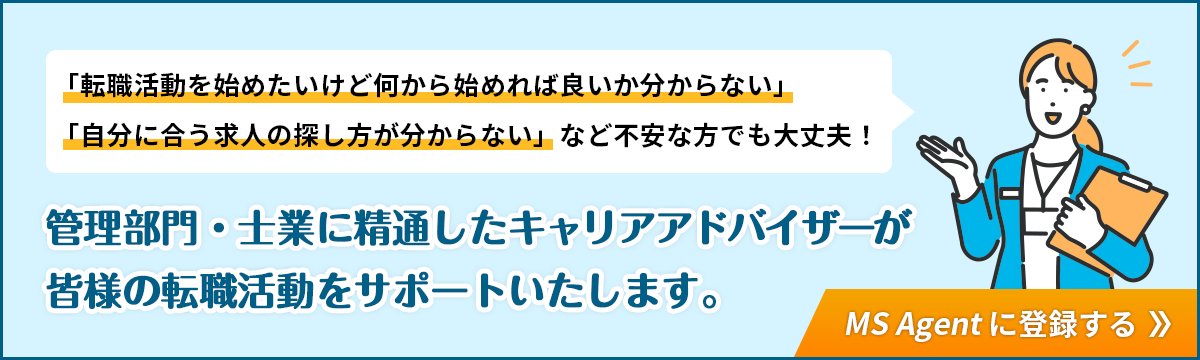
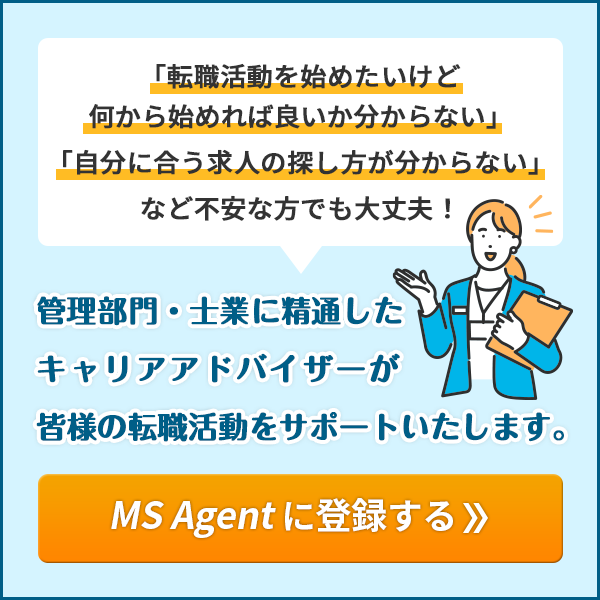
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、新卒でMS-Japanに入社。
法律事務所・会計事務所・監査法人・FAS系コンサルティングファーム等の士業領域において事務所側担当として採用支援に従事。その後、事務所側担当兼キャリアアドバイザーとして一気通貫で担当。
会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ コンサルティング ・ 金融 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事
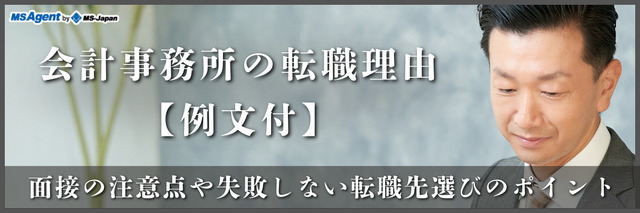
会計事務所の転職理由【例文付】面接の注意点や失敗しない転職先選びのポイント
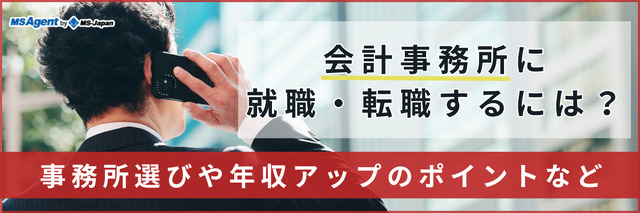
会計事務所に就職・転職するには?事務所選びや年収アップのポイントなど
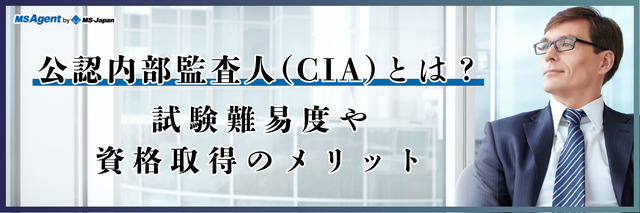
公認内部監査人(CIA)とは?試験難易度や資格取得のメリット
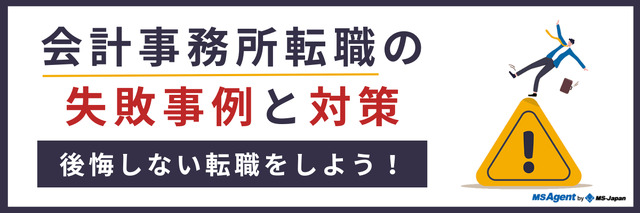
会計事務所転職の失敗事例と対策。後悔しない転職をしよう!
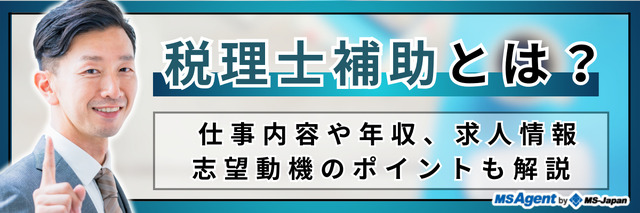
税理士補助とは? 仕事内容や年収、求人情報、志望動機のポイントも解説
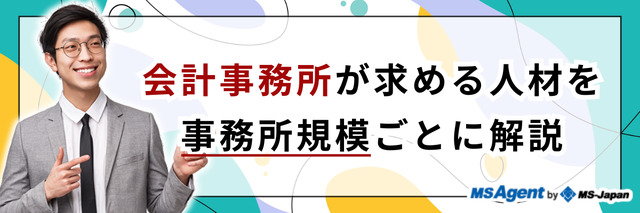
会計事務所が求める人材を事務所規模ごとに解説
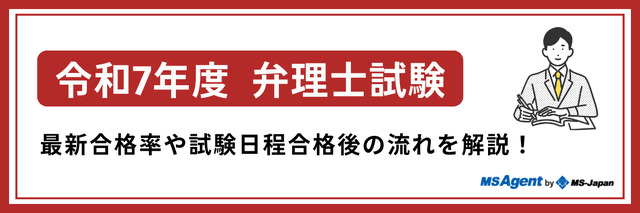
令和7年度弁理士試験|最新合格率や試験日程合格後の流れを解説!
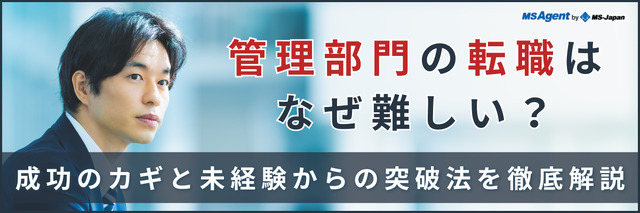
管理部門の転職はなぜ難しい?成功のカギと未経験からの突破法を徹底解説
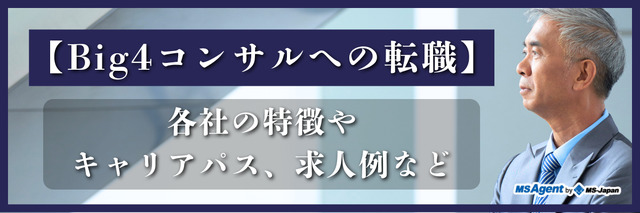
【Big4コンサルへの転職】各社の特徴やキャリアパス、求人例など
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。