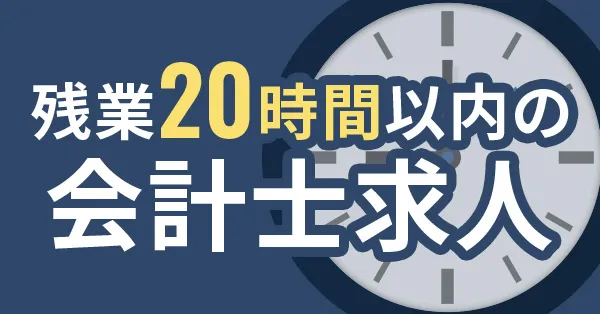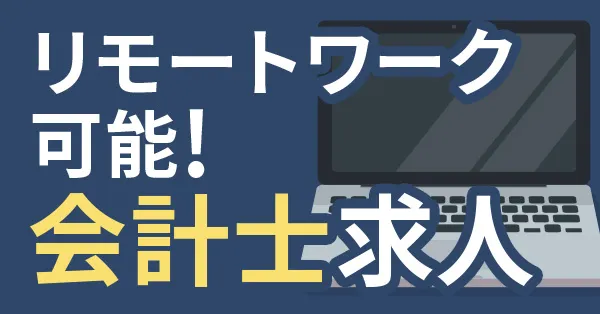公認会計士が独立した際によくある失敗は?後悔しないための準備とは
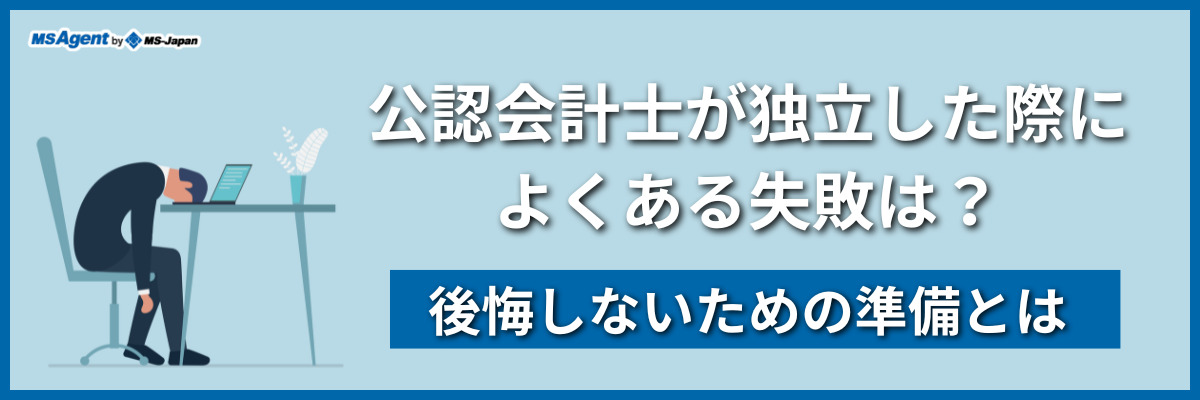
公認会計士として独立を目指す方の中には、「もし失敗したらどうしよう」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
実際、営業や資金繰りに苦戦し、独立を断念して再就職を考えるケースもあります。
この記事では、公認会計士が独立に失敗する主な要因とその回避策に加え、独立に失敗してしまった場合に取れる転職やキャリアの立て直し方まで詳しく解説します。
公認会計士として独立に失敗しても、再就職はできるのか?
独立を検討する公認会計士にとって、「もし失敗したらどうなるのか」と不安を感じるのは自然なことです。
取り返しがつかない状況になるのであれば、独立を思いとどまるべきかと迷う方もいるでしょう。
しかし、必要以上に心配する必要はありません。
仮に独立に失敗したとしても、公認会計士としてのキャリアを立て直す道は十分にあります。
現在の転職市場では、高度な会計スキルを持つ人材が不足しており、公認会計士の需要は依然として高い水準です。
監査法人はもちろん、一般企業における経理・財務・内部監査などのポジションでも活躍の場が広がっています。
とくに監査経験がある方であれば、監査法人への復帰は比較的スムーズです。
独立後に転職という選択をした会計士も少なくなく、失敗を経たとしても再スタートは十分可能です。
公認会計士の独立はリスクが高い?
独立のリスクは本当に高い?
「独立にはリスクがある」という印象を持つ方は少なくありません。
しかし、公認会計士に限っていえば、他の士業や一般的な起業と比べて独立のリスクは比較的低いといえます。
その理由は、公認会計士が監査やコンサルティングを通じて、多くの企業の経営実態に日常的に触れている点にあります。
成功事例はもちろん、失敗パターンも含めて現場に関わってきた経験は、独立後の経営判断に直結する実践的な知見となります。
こうした蓄積されたノウハウは、他業種の起業家では得にくい「経営の教科書」として大きな強みになります。
会計士ならではの強み
加えて、公認会計士はタスク遂行能力にも長けています。
監査法人や企業で培った「期限内に一定の成果を出す力」は、独立後の業務においても高い再現性を発揮します。
着実に成果を積み重ねれば、紹介やリピートの仕事が増え、安定した経営が可能になります。
反対に、スキルがあるにもかかわらず失敗するケースは、営業戦略や準備の不足によるものが多いのが実情です。
また、万が一収入が不安定になった場合でも、監査法人の非常勤勤務など柔軟な収入源を確保できる選択肢があります。
このように、公認会計士の独立は「リスクが低い上に、備えも取りやすい」という特性があると言えるでしょう。
公認会計士が独立に失敗する主な要因
公認会計士として独立することは、専門性を活かして自由な働き方を実現できる魅力的な選択肢です。
しかし、独立を目指すすべての公認会計士が、順調に成功できるとは限りません。
独立に失敗してしまう代表的な要因として、以下の5つが挙げられます。
- ・営業活動に問題がある
- ・差別化・ブランディングに失敗した
- ・ネットワーキング(人脈)不足
- ・プレッシャーに耐えられない
- ・料金設定のミス
営業活動に問題がある
クライアントは、「自分が独立する前の人脈から紹介してもらえばよい」と考える人もいるようです。
しかし、独立前の人脈の蓄えも、いずれ限界が見えてきます。
この時にマーケティングや営業の戦略に疎い、そもそも自ら顧客を開拓する営業が苦手という方は、早晩、営業活動に問題を抱えることになります。
会計事務所の経営を継続するためには、営業活動を行い新規のクライアントを開拓していくことは不可欠です。
具体的な営業の方法は、以下の方法が考えられます。
- ・監査法人や証券会社、ファンドなどの知人から紹介してもらう
- ・士業ネットワークやビジネスネットワークに参加して、仲良くなった参加者から紹介してもらう
- ・既存の顧客から紹介してもらう
- ・会計士紹介会社から紹介してもらう
また、上記の手法を実行するのと併せて、どのようなニーズに答えていくのか、競合優位性をどこで作るのかといったマーケティング戦略も必要になります。
せっかくの商談機会を得ても、営業活動がうまくいかず、新規のクライアントを獲得できなければ、独立に失敗するリスクは高まります。
差別化・ブランディングに失敗した
上述したマーケティング戦略について、差別化・ブランディングという観点で更に深掘りします。
公認会計士の人数は、年々増え続けています。
金融庁の「令和6年版モニタリングレポート」によると、2024年時点では約35,532人でしたが、今後もさらに増え続ける見込みです。
競争が激しくなる分、専門性や特徴を際立たせて、他の会計士と差別化・ブランディングしなければなりません。
公認会計士の差別化のポイントには、次のようなものがあります。
- ・他の事務所と比較して安い報酬で引き受ける
- ・英語力が高く、国際税務やIFRSなどの海外案件が得意
- ・IPO実績が豊富にある
- ・組織再編税制や連結納税などが得意
- ・特殊な業界の税務サービスに精通している
また、事務所のホームページやセミナーなどで、得意分野をアピールし、事務所をブランディングしていくことも大切です。
差別化・ブランディングに失敗すれば、他の公認会計士との競争に打ち勝つことができず、クライアントを集めることは難しくなるでしょう。
ネットワーキング・人脈不足
独立において、専門スキル以上に重要といっても過言ではないのが「人脈」です。
どれだけ会計・税務の知識が豊富でも、仕事をもたらしてくれるのは人であるという現実は変わりません。
とくに独立直後は、自ら営業しなければ新規の顧客は得られません。
しかしもともと監査法人や企業の中で業務を遂行してきた会計士にとって、「営業」や「人的ネットワークの構築」は未経験の領域です。
思うように営業ができず、結果として収入が得られないというパターンはよくあります。
会計士業界では、横のつながりによる紹介で仕事が回ることも多いため、独立前からの人脈形成がとても重要です。
たとえば、以下のような方法で仕事を獲得できます。
- ・士業コミュニティからの紹介
- ・過去の勤務先(監査法人・事業会社)からの依頼
- ・異業種交流会での知人からの依頼
人脈が機能し、「信頼→紹介→案件→実績→さらなる信頼」というサイクルが回れば理想的です。
結果的に、営業に時間を割く必要が減り、自分の得意領域に集中しながらビジネスを拡大できます。
プレッシャーに耐えられない
独立後はすべての責任が自分に降りかかります。
仕事の受注や納期管理、品質維持、顧客対応、場合によってはクレーム処理までワンオペでこなさなければならない状況もあります。
法人に所属していた時にはチームで支え合えていた作業も、独立すると自分一人で意思決定しなければならなくなります。
さらに独立すると、仕事だけではなく、税金や保険など本来であれば会社がやってくれていた手続きもこなさなければなりません。
特に独立初期は思うように売上が上がらなかったり、集客に苦戦したりと、精神的な負担が増す傾向があります。
そうしたなかで「プレッシャーに耐えきれず、精神的に消耗してしまう」というのは、決して珍しい話ではありません。
独立後に継続的に活動するためには、メンタルの安定が不可欠です。
信頼できる相談相手やメンターを持っておくこと、仕事量をコントロールする手段を身につけることも、長く続けるために重要です。
料金設定のミス
独立後に意外と多い落とし穴が、「料金設定のミス」です。
顧客を多く獲得するのは重要ですが、その思いが強すぎるあまり、相場よりも大幅に安い価格を提示してしまうケースがあります。
安すぎる価格設定は、長期的に見て収益悪化や財務リスクを招く原因になります。
会計士業務は労働集約的な側面が強いため、単価が低いまま仕事量を増やすと、「時間と体力を消耗するだけで利益が残らない」という事態に陥りかねません。
また、一度「安い会計士」というイメージが定着してしまうと、そこから単価を引き上げるのが難しくなります。
結果として、「忙しいのに儲からない」「自分の時間がまったく取れない」といった悪循環に陥ります。
適正な価格を設定するには、業務にかかる時間や、自分の仕事の価値、他の会計事務所の料金体系などを総合的に比較・分析する作業が必要です。
価格ではなく、サービスの内容で差別化を図り、顧客の信頼を得ることが重要です。
独立に失敗したらどうすればいい?
公認会計士の独立に失敗した際に重要なのは、「ブランクを作らない」ようにすることです。
自分の事務所をたたむ際には、従業員やクライアントへの対応など、山のように業務が出てきます。
それらの業務に忙殺され、自身の身の振り方を後回しにしてしまう例も多く見られます。
しかし、公認会計士の業界事情は、日々刻々と変わっていきます。
再就職において長いブランクはリスクとなるため、注意が必要です。
公認会計士として独立に失敗した後のキャリア
独立に失敗した後の公認会計士のキャリアは、監査法人や会計事務所、あるいは一般の事業会社が考えられます。
監査法人・会計事務所
独立に失敗した場合でも、監査法人や会計事務所に出戻りすることは可能です。
個人事務所の立ち上げを経験した人は、公認会計士として鍛えられているとみなされて、転職市場で高く評価されるケースもあります。
Big4をはじめとする大手監査法人でも、出戻り組の需要はあります。
一般事業会社
企業内会計士を募集している一般事業会社への転職も検討することができます。
中堅~大手クラスの事業会社なら、ワークライフバランスを取りながら落ち着いて仕事ができるでしょう。
また、ベンチャー企業のCFO候補や経理部門への転職も十分考えられます。
【公認会計士の独立失敗】よくある質問
最後に公認会計士の独立に関してよくある質問と回答を紹介します。
Q.独立を後悔する公認会計士の特徴は?
A.
独立を後悔する公認会計士には、いくつかの特徴があります。
代表的なのが「十分な準備不足」と「現実とのギャップに対する認識不足」です。
独立前に想像していた「自由さ」「高収入」が簡単に手に入ると思い込んでいると、営業活動やクライアント獲得の難しさに直面して失敗しやすくなります。
また、「人脈だけで仕事が集まるだろう」と安易に考えている場合も失敗しやすい特徴です。
独立後は新規営業やマーケティング、ブランディングが必要不可欠であり、これらを怠ると後悔する結果になりかねません。
後悔を防ぐためには、独立前に現実的な計画を立て、自分の強み・弱みを把握し、営業活動や経営の勉強をしっかり行うことが重要です。
Q.公認会計士が独立失敗後、再就職に影響しないブランク期間はどのくらいですか?
A.
再就職を目指す際は、自分のクライアントの整理をつけてから「半年以内」を目安に再就職先の決定が出来ると良いでしょう。
ブランク期間が半年を超えると、面接時に企業側から「その間何をしていたのか」とネガティブに評価されるリスクが高まります。
また、公認会計士の業務は日々変化する税務・会計のルールや制度に対応する必要があるため、長期ブランクはスキルや知識面でも不利になります。
ブランクを最小限に抑えるためには、「独立に失敗した」と感じた時点で早期に行動を起こすことが重要です。
たとえば、副業やフリーランス案件を受けながら再就職活動を進めることで、スキル維持と同時に経歴上の空白を回避できます。
Q.再就職時に年収ダウンは避けられないのでしょうか?
A.
公認会計士が独立失敗後に再就職する場合、短期的に見ると年収が下がるケースは多い傾向があります。
とくに独立前のキャリアが監査法人や大手企業の場合、独立失敗後の転職先でそれと同水準の年収を維持するのは難しい場合もあります。
しかし、必ずしも収入が下がるとは限りません。
独立時に磨いた営業力や経営者視点、専門性を明確にアピールできれば、企業側も高く評価してくれる可能性が十分あります。
また独立前の職場に戻る、いわゆる「出戻り」であれば独立前と同じ待遇で迎え入れてもらえるケースもあります。
年収ダウンを避けるためには、自身のスキルや経験を職務経歴書や面接で効果的に伝えることが大切です。
まとめ
公認会計士としての独立は、自由な働き方ややりがいのあるキャリアを築ける可能性がある一方で、準備不足や想定外の壁により失敗するリスクもあります。
しかし、仮に独立がうまくいかなかったとしても、それでキャリアが終わるわけではありません。
公認会計士という国家資格と実務経験は依然として高い価値を持ち、監査法人や一般企業など、再び活躍できるフィールドは豊富に存在します。
大切なのは、独立に対する現実的な理解と、柔軟にキャリアを設計し直す姿勢です。
失敗を恐れて行動を止めるのではなく、準備を整えたうえで挑戦し、万が一の場合はすぐに軌道修正すれば、長い目で見て納得のいくキャリアを築けます。
再就職の際は、独立失敗をマイナスと受け取られないよう、応募書類作成や面接対策を入念に行うのが重要です。
弊社MS-Japanは公認会計士をはじめとした士業・管理部門専門の転職支援を行っています。
創業35年のノウハウをもとに、多くの公認会計士の転職をサポートして参りました。
専門のアドバイザーによる書類作成や面接対策などの準備が必要であれば、ぜひご相談ください。
- #公認会計士
- #会計士の独立
- #独立開業
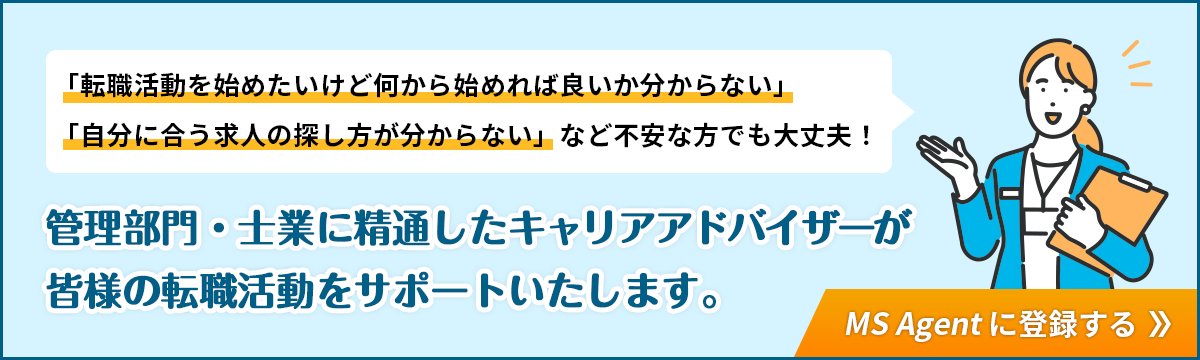
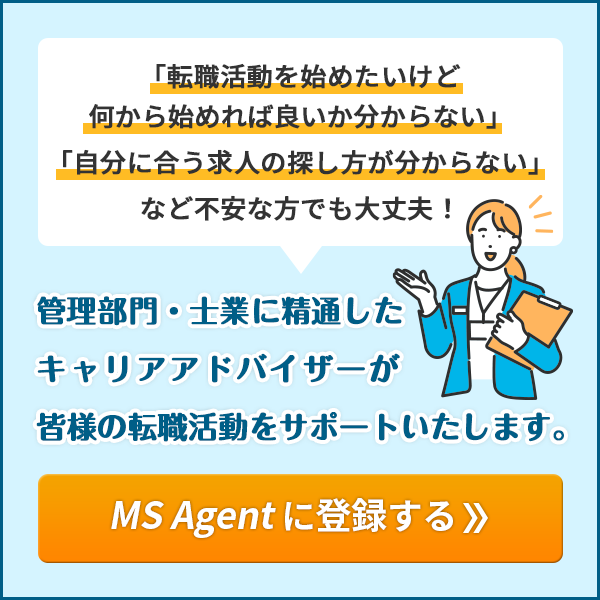 会計士TOPに戻る
会計士TOPに戻る
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、幸せに働く人を増やしたいという想いから新卒でMS-Japanに入社。
上場企業を中心とした求人開拓から管理部門全般のマッチングを行い、2021年1月より専門性の高いJ事業部に異動。
主に会計事務所、監査法人、社労士事務所の担当を持ちながら士業領域での転職を検討している方のカウンセリングから案件紹介を両面で行う。
会計事務所・監査法人 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ USCPA を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

公認会計士の独立|注意点やメリット・デメリット、必要な準備など
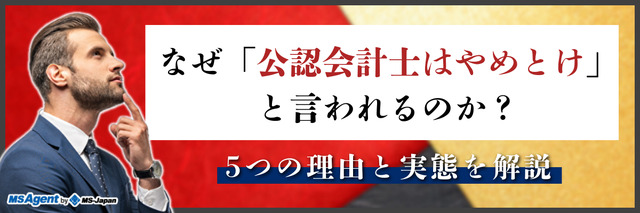
なぜ「公認会計士はやめとけ」と言われるのか?5つの理由と実態を解説
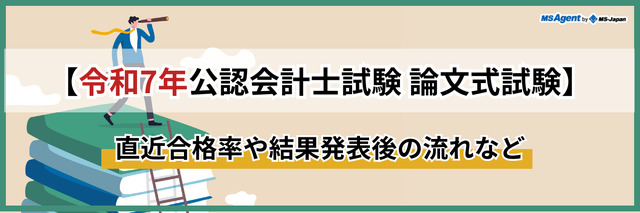
【令和7年公認会計士試験|論文式試験】直近合格率や結果発表後の流れなど
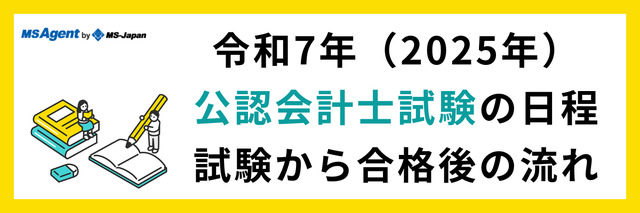
令和7年(2025年)公認会計士試験の日程|試験から合格後の流れ
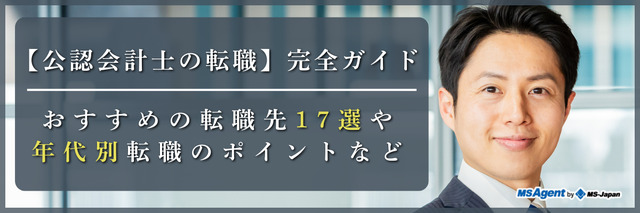
【公認会計士の転職】完全ガイド|おすすめの転職先17選や年代別転職のポイントなど
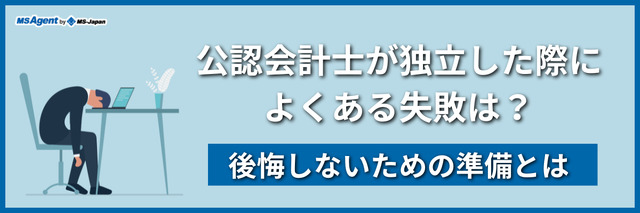
公認会計士が独立した際によくある失敗は?後悔しないための準備とは
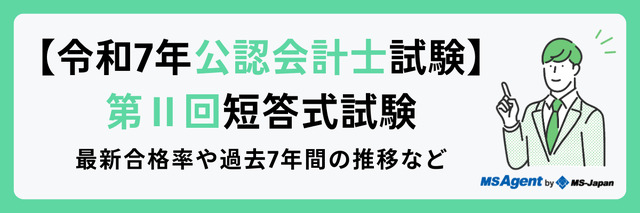
【令和7年公認会計士試験|第Ⅱ回短答式試験】最新合格率や過去7年間の推移など
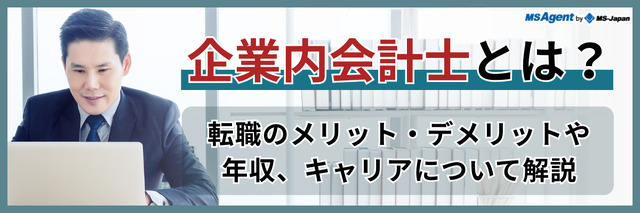
企業内会計士とは?転職のメリット・デメリットや年収、キャリアについて解説
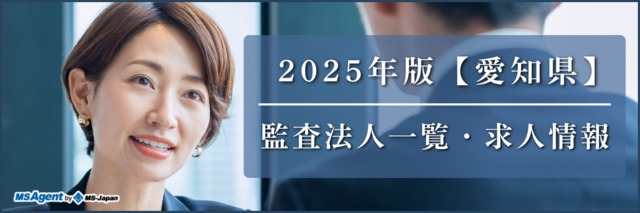
2025年版【愛知県】監査法人一覧・求人情報
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会
-
はじめてのキャリアカウンセリング
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
公認会計士の転職に強いキャリアアドバイザーとの個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
USCPA(科目合格者)のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
公認会計士短答式試験合格者のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
初めての転職を成功に導く!転職活動のポイントがわかる個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く
MS Agentの転職サービスとは
大手上場企業や監査法人、会計事務所(税理士法人)など、公認会計士の幅広いキャリアフィールドをカバーする求人をもとに、公認会計士専門のキャリアアドバイザーがあなたの転職をサポートします。
キャリアカウンセリングや応募書類の添削・作成サポート、面接対策など各種サービスを無料で受けることができるため、転職に不安がある公認会計士の方でも、スムーズに転職活動を進めることができます。

会計士が活躍する7つのキャリア
MS Agentを利用した会計士の
転職成功事例
転職成功事例一覧を見る
転職やキャリアに関する悩みを
転職FAQで解決!
公認会計士が外資系企業に転職するメリットは何ですか?
公認会計士が外資系企業に転職するメリットは、「自分のペースで仕事ができる」「日系企業に比べて年収が高い」の2つです。 外資系企業は良くも悪くも実力主義のため、成果を出すことができていればプライベートの時間も確保しながら仕事をすることができます。 また、日系企業に比べて年収が高い傾向がありますが、福利厚生は日系企業の方が充実しているため、年収と福利厚生のどちらを重視するかを検討する必要があります。
公認会計士は外資系企業でワークライフバランスを重視した働き方が出来ますか?
外資系企業は日系企業に比べて実力主義な傾向が強いため、自分で労働時間を管理することができます。 また、今では日系企業でもリモートワークを採用している企業が多いですが、外資系企業は日系企業よりもリモートワークが普及しているため、働き方という意味でも外資系企業ではワークライフバランスよく働くことが可能です。
公認会計士は外資系企業でどのような部門に配属されることが多いですか?
公認会計士が外資系企業に転職する場合、「アカウンティング部門」もしくは「ファイナンス部門」のいずれかが有力な選択肢となります。 アカウンティング部門は、日系企業でいう経理部に当たり、ファイナンス部門は日系企業でいうと予算管理部門と経営企画部門のちょうど間ぐらいの立ち位置になります。
公認会計士が外資系企業で働くにはどのようなスキルが求められますか?
公認会計士が外資系企業で働くには、本国の経営陣や従業員とビジネス的な会話ができるレベルの語学力が必要です。 また、本国の所在地にもよりますが、US-GAAP、IFRS/IASといった海外の会計基準と日本の会計基準の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 日本の公認会計士だけでなく、USCPAなどを取得しておくと外資系企業への転職には有利になります。
公認会計士が外資系企業に就職・転職するハードルは高いですか?
公認会計士が外資系企業に就職・転職するハードルは決して低くはありませんが、IFRS(国際財務報告基準)に関する知識と経験がある方には転職のチャンスがあります。 また、一定の英語スキルも必要にはなりますが、入社時に極端に高い語学力が求められるわけではありません。 尚、管理職を目指す場合は本国や他国の拠点とやり取りをするためにも、英語力は必須となります。

 を
相談できる!
を
相談できる!
求人を探す
勤務地で求人を探す
-
北海道・東北
-
関東
-
上信越・北陸
-
東海
-
関西
-
四国
-
四国
-
九州・沖縄